 政治家はなぜ「粛々」を好むのか―漢字の擬態語あれこれ (新潮選書)
政治家はなぜ「粛々」を好むのか―漢字の擬態語あれこれ (新潮選書)
本書は、中国古典などで使われた”漢字の擬態語”が日本に伝わった後の現代に於いても生きている言葉を、『論語』や『史記』をはじめ有名な詩人たちが残した漢詩などから多くを取り上げて解説している。中国から伝わってきた擬態語が長い年月使われているうちに、現代の日本に於いては微妙に違った意味で使われるようになったのが何故なのかを、本書で著者の考えを分りやすく述べている。『政治家はなぜ「粛々」を好むのか』というこの本のタイトルから、私が閃いたのは、頼山陽の漢詩『題不識庵撃機山図』第一行目の「鞭声粛粛夜過河」であった。「粛々」は、もとは、”漢字の擬音語”由来の”漢字の擬態語”の典型だったから「しずしずと」という解釈であろうが、「鞭声粛々」というこの漢詩から伝わってくる意味には、少し重いものを感じるのは私だけではないだろう。やはり本書の終わりで著者が「粛々」の解説で、上杉謙信が川中島で決戦を挑むため馬に打つ鞭の音も控えながら千曲川を進む描写から、「粛々」という言葉には、「しずしず」と進めるという決意のようなものを感ずると説いている。さらに著者は、この頼山陽の漢詩で使われた「粛々」という言葉を、多くの政治家が、聴く側に決意のような重みを与えるだろうと期待しながら好んで使うようになったのだろうと結んでいた。近頃の政治家のお歴々が「粛々」を、このように多く乱用していると、あと何十年もしたら「粛々」の意味も軽くなって違う意味になっているかも知れない。本書で「お歴々」の意味も軽くなってきたと書いていたから、軽い政治家たちが「粛々」と原発再稼働などを進める嫌な時代になってしまった、と私は最近の新聞などを、「辟易」としながら読んでいるのです。「辟易」という言葉も『史記』に書かれている頃は、「場所を変えて、相手の通り道を開く」という意味だったそうですが、私の使った「辟易」は、今の日本で一般的に使われている「うんざりする」という意味ですから誤解されないよう書き添えておきます。本書は、中国の思想家や詩人などが書き残した”漢字の擬態語”だけを取り上げ、日本人が何世紀もかけながら中国文化を日本文化として咀嚼しつつ変容していった過程を理解しながら興味津々で読み終わった一冊でした。 政治家はなぜ「粛々」を好むのか―漢字の擬態語あれこれ (新潮選書) 関連情報
このドリームハンター麗夢(レム)は友達の中でも、伝説化してます☆主人公の綾小路 麗夢の不思議な魅力に虜になります(笑)ぜひDVD化してほしいものです☆自分は中でも、この聖美神女学園の妖夢は一番好きでお勧めです!ぜひ一度見てみてください☆ ドリームハンター麗夢2~聖美神学園の妖夢 [VHS] 関連情報
このドリームハンター麗夢(レム)は友達の中でも、伝説化してます☆主人公の綾小路 麗夢の不思議な魅力に虜になります(笑)ぜひDVD化してほしいものです☆自分は中でも、この聖美神女学園の妖夢は一番好きでお勧めです!ぜひ一度見てみてください☆ 関連情報
価格が高めなので、一番好きな呉のみを購入。Not So BadとCarry onは相当いいです。聴くべきです。 真・三國無双7 キャラクターソング集2~呉~ 関連情報
この本は、鎌倉時代を実証主義に客観的に公平に記述したものです。鎌倉幕府政治、後醍醐天皇の政治を政治史として辿っていきます。惜しむらくは龍粛氏「鎌倉時代」1957年春秋社刊の抄録です。底本の目次から見ると「鎌倉時代の政治」「蒙古侵寇前後の対外関係」が採録されていません。よって星四つ。他は鎌倉幕府の文献的な史料批判です。 この書は、1960年代から1990年代に出版された鎌倉時代史とは一味違っています。あとがきのの解説にあるように皇家と貴族、武士の葛藤を実証的に描いています。また、「元寇の防衛と国民精神の昂揚」は以後の日本国の国民性、中世武士道のきっかけとなる重要な部分です。源頼朝が京都を憧憬し武士が皇家、貴族の文化に迫ろうとする武家文化の気概を感じさせます。京都との関係を意識しその維持に腐心する頼朝の苦悩も感じ取れます。いわゆる南北朝政治の天皇親政への準備を進める後醍醐天皇、一方では皇位継承が行き詰まり閉塞状況下の南北両朝の動きが公平に描かれています。 これまでの中世鎌倉時代を政治史的に追ったものは専門的に過ぎ分野が細分化しています。「鎌倉時代を概観」する時に基本事項としてこの本の内容程度は理解しておかねば中世、鎌倉時代のアウトラインとなる「鎌倉幕府は武家政治に始まる」ことが見えません。この分野に興味ある方にはお勧め、必読書です。 鎌倉時代 (文春学藝ライブラリー) 関連情報

![ドリームハンター麗夢2~聖美神学園の妖夢 [VHS] 粛々](../template/img/noimage_m.gif)












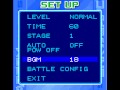





![カタチ新発見! 立体ピクロス2 [オンラインコード] カタチ新発見! 立体ピクロス2 [オンラインコード]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B0142I9K8I.09.MZZZZZZZ.jpg)

![[アディダス] adidas フットサルシューズ エックス 15.1 CG [アディダス] adidas フットサルシューズ エックス 15.1 CG](http://images-jp.amazon.com/images/P/B0111XYA2S.09.MZZZZZZZ.jpg)
![ミニオンズ ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray] ミニオンズ ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B00YTKIYZA.09.MZZZZZZZ.jpg)



![奈良美智 ドローイング作品集 YOSHITOMO NARA NO WAR! ([バラエティ]) 奈良美智 ドローイング作品集 YOSHITOMO NARA NO WAR! ([バラエティ])](http://images-jp.amazon.com/images/P/4568104823.09.MZZZZZZZ.jpg)

