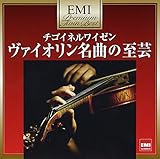 プレミアム・ツイン・ベスト チゴイネルワイゼン~ギトリス~ヴァイオリン名曲の至芸
プレミアム・ツイン・ベスト チゴイネルワイゼン~ギトリス~ヴァイオリン名曲の至芸
テレビなどでよく聴くおなじみの名曲が収録されています。ギトリスからあふれ出す音色に心を打たれました。 プレミアム・ツイン・ベスト チゴイネルワイゼン~ギトリス~ヴァイオリン名曲の至芸 関連情報
「日本に行く。実際に何が起こっているのかこの目で見なくてはならない。フランスからの渡航費はエールフランスに掛け合うし、私の来日にかかる費用は一切負担する必要はない。それから、出演料はいらないのでチャリティコンサートを行ってくれ」。東日本大震災と福島第一原発事故の後、多くの海外のアーティストが予定されていた来日公演をキャンセルした。しかし、当時既に90歳近かった1922年生まれのクラシック音楽界の巨匠バイオリニストがとった行動はそれとは逆だった。日本の愛弟子や音楽関係者たちとすぐに連絡をとり「一晩中寝ずに考えた。事情が許すようなら、すぐにでも日本に駆けつけたい」と語り、高齢をおして5月末に来日し、石巻市を訪れ、東京でチャリティコンサートを開き、内外のプレスの取材にも積極的に応じた。翌年以降も来日の度に陸前高田市などを訪れている。そんなギトリスは、自らもユダヤ人として第二次世界大戦と中東戦争を経験している。母親との折り合いも悪かったようだ。だが、けして暗い性格の人ではない。様々な人たちと交流を持ち、愛し、努力し、演じ、教え、年輪を重ねて生きてきたことが、本書の証言や記録を読むとよくわかる。「自分の中で表現の自由をじっくり育てるため、単にそのための手段としてテクニックはある」。フィリップ・クレマンの著作を3部に分けて再編集し、最後に日本の読者向けの記載を加えて作られている。正直、あまりまとまりのいい本ではない。ただ、ギトリス本人のインタビューや著作からの引用だけでなく、様々な人たちのコメントがふんだんに掲載されており、この大御所が、世界中の音楽家たちから愛されていることがよくわかるようになっている。「ニュアンスというのは、ヴァイオリニストができる限り行うべき三つの要素が複合した動きのことだ。三つとは、力強さ、音色、ルバート。三つそれぞれが音の文体を形作り、耳に届いて音楽の流れるラインとなる」。個人的な話になるが、私もこの人の演奏を聴くために2013年に紀尾井ホールに足を運んだことがある。時にトークを交えながら、普通のコンサートとは明らかに違うオーラに包まれていた。そもそも、こんな高齢で現役のバイオリニストとしての技巧を維持できていることが驚きだ。19世紀的とも称される独特のスタイルは、時に批判の対象となることもあるが、スキのない現代的で画一的な演奏とは明らかに違う個性を放っている。「ヴァイオリンを弾くことは、私にとってただ『ヴァイオリンを弾く』じゃなくて生き方なんだ」。冒頭部分にはカラー写真が10ページ以上にわたって掲載されている。本文においても、解像度はよくないが、白黒の写真が時々収められている。 イヴリー・ギトリス ザ・ヴァイオリニスト 関連情報
藤谷文子さんが出演しているので買ってみました。内容も面白い!最近観た映画の中でも一番面白いと思いました。主人公がもう少しゆっくりと世界を巡れば言うことなしでした。と言っても時間などの問題があるので仕方が無いんですけど全体の雰囲気は「バグダッドカフェ」に近いところがあると思います。あとはひたすらに主人公に憧れる映画です。ハプニングや事件が無く平らな映画ですが、そこが最高なのです。アクション映画が大好きな人には耐えられない内容かもしれません。この映画を観て面白いと思った方には是非、庵野秀明監督の初実写映画「式日」がお勧めです。 サンサーラ [DVD] 関連情報
心象表現が丁寧に書かれた内容。日本人からすると想像出来ないような環境で育った少年時代の話はフィクションを越える不思議な登場人物の物語になっている。作家の手によるもに思えるほど完成度は高いと感じられ、再版されて欲しいと思う。演奏家の方には勇気を与えてくれる部分が少なからずあると想像する。ギトリスの演奏を好まない人でも読んで欲しい。同時代の演奏家を評論したような表記やエピソードはそれほど多くなく、資料としての読み応えはあまり無いかもしれない。 魂と弦 関連情報
どこをとってもイヴリー・ギトリスという濃密なショートピーシーズだ。それゆえ、こうしたアンコール有名曲を初めて聴く人には向かない。五嶋みどりでも諏訪内晶子でも、もっと凛とした正統派の演奏で聴いてからにしたほうがよい。そして、必ず最期にはギトリスを聴くべきなのである。チョン・キョンファの格調が高く別次元の小品集とは趣きが全く異なるが、地の底から這い出してくるような、なおかつ芸術的にはチョンと同格の演奏といえよう。「歌の翼に」「美しきロスマリン」など、かつて聴いたこともない、ほとんどこの曲とも思えない濃厚さだ。後者はベルリオーズの『幻想交響曲』めいている。「亜麻色の髪の乙女」は幾らなんでもという粘着的な調べと怨念さえ漂う。絶対にこの演奏で最初に聴いてはいけないのがこの曲。チャイコフスキーの「感傷的なワルツ」もよく聴いていると怖いところがある。マリーの「金婚式」はスタンダードに近いが、どこか底知れない闇のようなものを思わせもする。白眉は、ドヴォルザークの「フモレスケ」と最後に入っている「ツィゴイネルワイゼン」だ。ギトリスの調べには、長調のなかにさえ短調の絵の具が混じっている。しかも感傷的な愁いというよりは、放浪の悲愁、サーカスの哀愁、旅芸人の諧謔だ。彼は悲しがっているのではない。生まれたときから悲嘆やペーソスが身に染み付いているのだ。それが人生なのだと言わんばかりである。「フモレスケ」は、テーマの揺れからして思わず耳を欹てるに十分。すでに哀しみがこもっている。これが短調のテーマ転じると荒涼とした地を彷徨えるギトリスその人を幻視させるかのようだ。ドヴォルザークの哀しみさえ。凄い音楽だと思わせる。本来何のことはない小品なのだが・・・。「ユーモアとは哀しみの一形式」であると言わんばかりに。「ツィゴイネルワイゼン」はまさにギトリスのための音楽だ。ロマの歌。ユダヤ人ギトリスはロマたちの悲嘆を本能で感じているのか? その魂が深いところから響いてくる。ピチカートひとつが聴く者の心に突き刺さってくるのだ。作品前半、ピアノソロが入ってきてやがてピアニッシモで奏される前半の終結へ向う部分などは、評すべき言葉もない。振幅、強弱いずれも厳しく、激しい。楽想は伸び縮みし、自由自在である。表現はほとんど悪魔的。後半のチャルダーシュなど不要と思わせるほどだ。この曲はハイフェッツ盤が長らくベストとされてきたが、ギトリスを聴いてしまったらもうだめだ。麻薬的であり、あまりにも哀しくて、これを聴くだけでもどっと疲れてしまう。こんなに深い作品なのか? 同じユダヤ系でも、ハイフェッツとはまるで違う表現だ。これで見ても人種などは表現に関係はないとわかる。教育環境の違いなのだろうか?繰り返すが、初心者には向かない。下手をすれば、これらの作品を嫌いになってしまう可能性だってある。よく聴いている人でも、この演奏は嫌いという人が結構多いのではないだろうか。 ヴァイオリン名曲集ア・ラ・カルト 関連情報


![サンサーラ [DVD] イヴリー・ギトリス](http://ecx.images-amazon.com/images/I/211E9RXC9AL._SL160_.jpg)
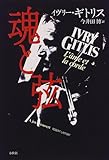





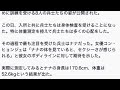


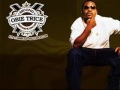









![ガールズ&パンツァー これが本当のアンツィオ戦です! [Blu-ray] ガールズ&パンツァー これが本当のアンツィオ戦です! [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B00IIEERM2.09.MZZZZZZZ.jpg)







