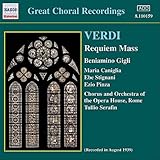 ヴェルディ:レクイエム(ジーリ/カニーリア/セラフィン)(1939)
ヴェルディ:レクイエム(ジーリ/カニーリア/セラフィン)(1939)
アイヴィーと言えば、ナクソス。廉価版の演奏を出していることで有名であり、「オレはそんな二流演奏家のものなんか買って聴きたくない」と金持ちぶる人もいることだろう。だが、クラシック好きならば、少なくともナクソス・ヒストリカルの往年の名指揮者の演奏に耳を傾けたくるべきだ。古い放送音源であったりすることで、音の悪さは確かに否めないものの、ぜひ聴いておきたいものだ。で、今回推薦しようというのが、セラフィンのヴェルディ「レクイエム」。セラフィンというと、マリア・カラスが歌うヴェルディのオペラの指揮をしてたっけ、という認識が一番強いのだが、ただの伴奏じゃない。実力派のヴェルディ振りの職人です。ですから、ヴェルディの語法というのをよくわかっています。このヴェルディのレクイエムを録音する指揮者は、どうしてもモーツァルトやフォーレのレクイエム、もしくはブルックナーのテ・デウムなどといった「宗教曲」としての括りと同様に演奏しているような気がします。しかし、このヴェルディのレクイエムは他の宗教曲とは一線を画します。非常にドラマチックに描かれているのです。だからこそ、オペラのノリを知っているセラフィンの取り組みには期待していいのです。今回は私がいろいろどこがいいのどこが悪いのと言うのはやめておくことにします。その方が楽しみ方が無限の可能性を秘めているような気がするので。 ヴェルディ:レクイエム(ジーリ/カニーリア/セラフィン)(1939) 関連情報
セラフィンはスカラ座黄金時代にカラスやテバルディなどのスター歌手を起用したイタリア・オペラを中心とする劇場作品の全曲録音を数多く遺していて、それらは未だにオペラ上演史上燦然と輝く名演であることに間違いない。勿論この序曲集にもセラフィンの作品に対する演奏上の百戦錬磨のテクニックと劇場感覚的な秘訣が示されている。それはオペラ劇場という特殊な空間でこそ本来の効果を発揮するものだが、このCDでもその巧みさは充分に感知できる。そのひとつがオーケストラを呼吸させるように自由自在に歌わせるカンタービレで、しかも歌わせることによって緊張感が弛緩したり、音楽が冗長になることを完璧に避けている。それは彼が音楽構成の脈絡や起承転結を心得ていたからで、自然で大らかな歌の抑揚を横溢させながらドラマを進めていく手法は現在のイタリアのオペラ指揮者にも伝統的に受け継がれている。ここに収録されている序曲や前奏曲はいずれもシンプルなオーケストレーションだが直接聴衆の感性に訴えて、幕開けを準備する雰囲気作りに奉仕されている。トゥッリオ・セラフィン(1878-1968)はトスカニーニの後を継いでスカラ座の指揮者に就任してから国際的な演奏活動を始める。1923年からはニューヨークのメトロポリタン歌劇場にも10年ほど席を置いて、カルーソ亡き後のアメリカでのイタリア・オペラ隆盛にも貢献しているが、彼の劇場作品のレパートリーは多くの初演を合わせると243曲に上り、その中にはドイツ、ロシア物も含まれている。またローザ・ポンセルやマリア・カラスなどにイタリア風のカンタービレやベル・カントを伝授して歌手の育成にも寄与した。セラフィンは歌手の長所を巧みに引き出して、それを最大限活かす術を知り尽くしていたマエストロだったと言えるだろう。アバドやムーティの時代に入ると過去の歌手達が慣習で歌っていたスコアには書かれていない装飾やカデンツァは一切排除する、いわゆる原典主義が定着するが、セラフィンの頃はまだ指揮者や歌手にも音楽への裁量がかなり認められていて、効果的な演奏と見做されれば拒まれなかった。そうした柔軟なアプローチがこの序曲集を精彩に富んだものにしているのも事実だろう。メディチ・アーツはBBC音源を中心にリマスタリングしたメディチ・マスターズ・シリーズをリリースしていた英国のレーベルで興味深いカタログを持っていたが、2010年以降新盤は出していない。現在ではメディチtvという名称でDVD主体の販売を行っていて、これらの映像はベルリンに本拠を置くユーロ・アーツでも扱っているが歴史的音源のリイシューCD盤は打ち切られたようだ。尚この序曲集は全曲ステレオ録音で、リマスタリングによって鮮明な音質が蘇っている。収録曲目ヴェルディ:『シチリアの晩祷』序曲 『椿姫』第1幕への前奏曲 同第3幕への前奏曲 『運命の力』序曲(1959年録音)以上ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 『ナブッコ』序曲 『アイーダ』第1幕への前奏曲(1959年) ベッリーニ:『ノルマ』第1幕への前奏曲(1961年)以上フィルハーモニア管弦楽団 同第2幕への前奏曲(1960年)ミラノ・スカラ座管弦楽団 ロッシーニ:『チェネレントラ』序曲 ドニゼッティ:『シャモニーのリンダ』序曲 『ドン・パスクワーレ』序曲(1961年)以上フィルハーモニア管弦楽団 セラフィン 関連情報
発展途上の作家さんですが今となっては逆に荒々しさが美点とも思える印象ですが実用性に関してヒットポイントが非常に少ないのでこのような評価になってしまいましたが、人によって感じ方も違うので原作者が反論できない所であーだこーだ書くのもアレですが、次回作にも少し期待って事で☆3つにさせてもらいました。 おかず少女 (セラフィンコミックス) 関連情報
久し振りにトゥリオ・セラフィンが指揮するローマ歌劇場管弦楽団のロッシーニ序曲集を聴いてみました。 トゥリオ・セラフィンはスカラ座、メトロポリタン歌劇場、そしてローマ歌劇場管弦楽団の音楽監督を務め、トスカニーニ、デ・サバータと並ぶイタリア・オペラの最高のオペラ指揮者として広くその名が知られていましたが1968年に亡くなっています。 指揮者としても優れた活動をしていましたがマリア・カラスを見出してベル・カント・オペラを教え名歌手として彼女を育成したことは良く知られたことです。 「どろぼうかささぎ」「セビリャの理髪師」「ウイリアム・テル」等の序曲ではローマ歌劇場管弦楽団の煌びやかなブラス群と弦楽群のアンサンブルの素晴らしさ、その実力には思わず快哉を上げたくなる衝動に駆られてしまいます。 現代では、もはや、このような音楽性豊かな演奏に出会えることはないでしょう。 また、録音も素晴らしく、現在のマルチ・トラック録音では得られない自然な音の広がりは、まるでコンサート会場で聴くような臨場感に溢れています。 ラストの「セミラーミデ」序曲を聴き終えた後の感動はどのように表現したらよいのでしょうか。心から酔える素晴らしい演奏に出会った夜、心温かに東京文化会館の坂道を下るのに似ているといった方が良いでしょうか。 このような素晴らしいCDも今では輸入盤以外では入手困難となってしまいました。国内でも是非、商売は抜きにして再発して欲しいCDの1枚です。 ロッシーニ:序曲集 関連情報
 MAMA IN CAR 妊婦さん 乗車中 ( 12cm その1 四角 )( マグネット ステッカー )( マタニティ マーク 外貼り デザイン )
MAMA IN CAR 妊婦さん 乗車中 ( 12cm その1 四角 )( マグネット ステッカー )( マタニティ マーク 外貼り デザイン )
見ていたら、思わず買ってしまいました。なかなか、気に入っています。 MAMA IN CAR 妊婦さん 乗車中 ( 12cm その1 四角 )( マグネット ステッカー )( マタニティ マーク 外貼り デザイン ) 関連情報

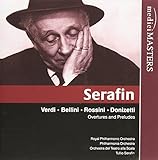












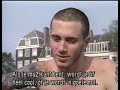


![戸田れい/どっちにするの [DVD] 戸田れい/どっちにするの [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B016MG4NO4.09.MZZZZZZZ.jpg)




![ジャンプ流! 2016年 2/18号 [分冊百科] ジャンプ流! 2016年 2/18号 [分冊百科]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B01AS1UYX8.09.MZZZZZZZ.jpg)




![【Amazon.co.jp限定】ドラゴンボールZ 復活の「F」 特別限定版(初回生産限定)(描き下ろしB2布ポスター付き) [DVD] 【Amazon.co.jp限定】ドラゴンボールZ 復活の「F」 特別限定版(初回生産限定)(描き下ろしB2布ポスター付き) [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B010CKC2HQ.09.MZZZZZZZ.jpg)